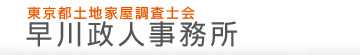GPS
Global Positioning Systemのイニシャルで、アメリカ合衆国が、航空機、船舶等の航法支援用として開発したシステムをいう。上空約2万kmに打ち上げられている24個の位置測定用の人工衛星から発信された電波が受信機に到達する時間によって位置を求めている。測定方法によって以下の四方法に分けられる。
①単独測位:1台の受信機で測定する方法で、10mの誤差で位置が決定できる。自動車や飛行機のナビなどに利用されている。
②相対測位:2台以上の受信機で2点間の相対的な位置関係を測定する方法で、リアルタイムではないが、100万分の1(2点間が10kmで1cmの誤差)の精度の測定が可能である。
③ディファレンシャルGPS、RTK-GPS測位:位置のわかっている基準局と、求めようとする観測点で同時に観測を行い、基準局で観測したデータを無線等で観測点に送信し、リアルタイムに位置を求められる。ディファレンシャルGPSは両点での単独測位で行い数m、RTK(Real Time Kinematicの略でリアルタイム測定)-GPSは両点で位相の観測を行い数cmの誤差で測定が可能である。
④リアルタイム測位システム:VRS(Virtual Reference Station 仮想基準点)方式、ネットワーク型RTK-GPSなどと呼ばれ、国土地理院が設置した全国約1000箇所の電子基準点と携帯電話等を使って基準点等を精度良く測定するシステムである。
日本測地系
世界測地系に対応した言葉で、最近まで測量法で定められていたわが国独自の位置及び高さの基準と地球の形に基づく緯度経度の基準をいう。最近のGPS測量など国際的に統一する動きの中で、測量法が平成13年6月改正され、世界の基準と整合を取るようになった。これに伴い、場所により若干異なるが、緯度経度の値がそれぞれ11秒(距離にしてそれぞれ450m程度で、同じ地点では東経の値では減少し、北緯の値では増加)変更となっている。
世界測地系
国際間で共通に用いる地球上の位置の座標系をいう。平成13年に改正された測量法でも、測量の基準は世界測地系で行うこととなり、そのための基準が定められている。
ジオイド
静止している海水面が地表にも続いていると仮定した面で、それぞれの地点での高さの基準となる面である。これは地球内部を構成している物質による重力で水面の高さが異なってくるからである。
電子基準点
国土地理院がGPSで常時観測している基準点で、全国に約1200点設置している。この点は、地殻変動の監視、各種測量の基準点として利用されており、2003年からはリアルタイムのデータの提供が行われるようになっている。
登記簿
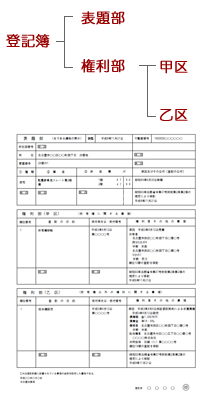
登記簿とは、表示に関する登記及び権利に関する登記について、1筆の土地又は1個の建物ごとに不動産の登記記録が記録されたの帳簿のこと。法務局に備え付けられています。
表題部:
土地の場合→ 所在・地番・地目・地積が記録される部分。
建物の場合→所在・家屋番号・建物の種類・構造・床面積が記録されるところ。
権利部:権利に関する登記記録がされる部分。
甲区:所有権に関する登記がされる部分。
乙区:所有権以外の権利(抵当権や賃借権、地上権など)に関する登記がされる部分。
地目(ちもく)
土地の主たる用途によって次の23種類に区分されます。1筆の土地に2種類以上の地目は認められません。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地。
筆界特定制度
筆界特定制度とは、筆界が不明な場合に、所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえ、筆界の位置を現地において特定する法務局の行う制度。
筆界特定登記官
登記官のうちから、法務局または地方法務局の長が指定する筆界を特定する業務を行なう者。
筆界調査委員
筆界および紛争について専門的な知識と経験を持つ土地家屋調査士・弁護士等の中から法務局、地方法務局の長が任命した者。